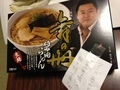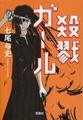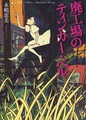|
William Olaf Stapledon オッド・ジョン [ honto / amazon / 国会図書館サーチ ] |
オラフ・ステープルドンの名前を知ったのは約20年前、大学生の頃だったと思う。
荒俣先生の書評でみて、読んでみたいと思ったが既に絶版状態。
ネットもAmazonも無い時代、地方在住の私にとっては秋葉原へ行くにもお金がかかる。
大学生時代に「Last and first men」を辞書片手に読み始めたが、最初のほうで挫折。
けっこう(時代背景的に)難しい単語が多くて続かなかった。
とかなんとかしているうちに「スターメイカー」が翻訳され(1990)、「最後にして最初の人類」も刊行(2004)。
そのうち「シリウス」が再刊され、日本語に翻訳されたものの最後が「オッド・ジョン」になった。
時々思い出したようにAmazonで探していましたが、
この度数年ぶりに探して見つけたのでポチリました。
閑話休題
新人類(個人)の覚醒からコミュニティの創造と終焉まで、
と要約してしまうとありきたりの物語みたい。
約80年前(1934)に書かれたものだけど、古さを感じない。
面白くて一気に読んだけど一般受けはしないだろうので、あまりオススメしません。
荒俣先生の解説も良かった。
参考:William Olaf Stapledon の翻訳モノ一覧