この物語を誰かに何て紹介しよう、思った時に。
舞台は架空の世界ですが、ファンタジーというのは本質をついていないし。
歴史物、というのも体はそうですが、伝わらない。
boy meets girlという言葉では物足りない。
私は恐らく、普通よりも少しだけ「言葉」に興味があると思う。
口承の言葉の民俗に興味があるのですが、
いかんせんそれらの本って文芸に限らず学術でも少ないようです。
そんな中でタイトルは知っていた「図書館の魔女」。
あまりにストレートな表題に腰が引けて手にとっていませんでした。
大部であるので、正月休みに読もうと「欲しいものリスト」に入れっぱなし。
GW前に文庫版1,2が出てたので、これを機会にと期待せずに読み始めると…
内容もタイトル通りストレートでした。
もとより寡聞にして人文系をきちんと勉強していない私には、全てが判るわけではないですが、
あぁ、言葉で遊んでいるんだなぁ、と感じられました。
以前に菅野洋子さんの曲を聴いて、音楽で遊んでいるんだ、と思った感じに似ています。
閑話休題。
今の時代だから分る言葉・言語の理屈や道理もあると思うのです。
だから、分類するとすれば、人文科学小説になるのかなぁ?
その考えが正しければ、これからももっと深い言葉の物語が出てくる可能性もあるわけですね。
勝手に期待して、首を長くして待ってみます。
20歳の差というのは…
お題目は変わっても

|
アクアリウムにようこそ ISBN 978-4-408-53585-2 [ honto / amazon / 国会図書館サーチ ] |
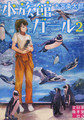
|
水族館ガール 2 ISBN 978-4-408-55240-8 [ honto / amazon / 国会図書館サーチ ] |
「アクアリウムにようこそ」私が買ったのはハードカバーなのですが、
今は文庫本が出ていて、タイトルも変わっていたのですね。
そして、続刊が出ました!
ままあることではあるけれど、本のタイトルが変わるということは。
中身が変わるわけではないのでいいんです。
というか、ラノベ世代が段々と歳を重ねて来た結果だと思うのですが、
文芸全般のラノベを狙った感じが強くなってきてますね。
内容的は比較的にオカタイものでも、
書影のイラストもキャッチーなものが増えてきた気がします。
タイトルもラノベっぽくなってきているかな?
私は今までタイトル(文字)で先ず本を探していたのですが、
気をつけないとなぁ、面白い本を見逃してしまうかも。
とまぁ、2巻を読む前に何となく。
これは酔っぱらいの話
思い描いた未来は、手の届く距離にある
from 星海のアーキペラゴ
何だろう、時々ですが、
よく聴いている曲でも、ふと涙が出てくる時があります。
ー 多田葵、ようこそ、太陽系へ。
3年前に買って、最近またよく聴いているのですが、
「あきらめるな、宇宙はそこにある。」とはまた違って、
いつも眼前に見えているものでも、その感覚を実感する瞬間というのでしょうか?
歳をとっているからこそ気付けるもの、というものもあるのでしょうね。
カワウソ+自転車
怪異の拡散と浸透と散逸
タイトルに深い意味はありません、多分。
なんというか、まぁ本屋に行くと怪異ブームですね。
一頃はミステリーブームでしたが、
最近はまぁ、移り変わりの激しいこと。
何か流行ると、一斉にそれ一色に染まり、
しばらくすると、波が引くように消えていきますね。
そんなご時世なので、本屋さんで本を選ぶのにも考えてしまいます。
そんな中、ひっそりではありますが、むしろ潔いタイトルを見つけたので手に取りました。
 |
皆藤黒助 ようするに、怪異ではない。 ISBN 978-4-04-102929-9 [ honto / amazon / 国会図書館サーチ ] |
ネタバレを避けるため詳しくは読んでのお楽しみですが、
私はとても楽しむことが出来ました。
個人的には、怪異譚は物理的な科学で云々するよりも、
人文的な面白さが楽しいと思うのですよ。
そういう意味でも、こういう方向の「お話」がもっとあってもいいと思うのです。
まぁ、こういう流行り廃りを繰り返して文化というものは進んでいくのでしょうね。
多分にcyclicなのでしょう。
翼を持つ本
 |
山本弘 翼を持つ少女: BISビブリオバトル部 ISBN 978-4-488-01820-7 [ honto / amazon / 国会図書館サーチ ] |
そうですよねー。
そろそろ 赤木かん子のSFセレクション 読んだ世代が大きくなって来る頃ですよ。
宇宙人だという成恵の背景はどうも複雑だ 2005年だから、もう10年ですよ。
閑話休題。
まだ第1章しか読んでないけど、面白いね!
ところどころ、ニヤリとしながら読み進めています。
あぁ、誰かとこの本を肴にして一晩語り明かしたいなぁ。
■追記 2015. 2.28
キャプテン・フューチャーだった。
私もそこそこ歳をとっているので、アニメ版キャプテン・フューチャーは生で見ていた口です。
内容はほとんど覚えていないのですが、やはり主題歌は覚えています。不思議ですね。
インターネットが普及し始めた2000年ころに、一度この主題歌を検索したのですが見つからなかった覚えがあります。
そして、2004年から刊行が始まった東京創元社のキャプテン・フューチャー全集で、初めて読みました。
昔はあかね書房のアレで読んだ程度でした。
エピローグに歌詞が載っています、懐かしいですね。
メロディーもはっきり覚えているよ。
甘じょっぱい青春
年末年始の積読消化
この休みは自分比でけっこう読みました。
久しぶりに、簡単に感想を、

宮内悠介, 盤上の夜
買おうか買うまいか迷ってた本を買って読むのが通例となっているのですが、その筆頭がこの本でした。
2014年、何度この本の前で迷ったことか。
そして、表題作が一番面白かった。
理屈を前面に出さずにお話を展開してくれるのが私の好みでした。

高山羽根子, うどん キツネつきの
これは上とは対照的に、パラ見でなんとなく買った本です。
こういうのが好きです。
と言っても、人に理解してもらうのが一番難しい、説明しにくい本です。

酒見賢一, 泣き虫弱虫諸葛孔明 第4部
酒見さんは安心して読めますね。
第三部までに比べ大人しめな感じがしましたが、これは主要メンバーがかなり亡くなって物語の山を超えたから?
それとも?

柴田勝家, ニルヤの島
うーん、まだ消化しきれてないです。
近いうちにもう一度読みたいけれど、
と言っているうちに一年たってそうな予感。

山本弘, プロジェクトぴあの
山本さんはいつもトンデモと科学の縫い目をするりと抜けていきますね。
ディティールは個人的には共感できなかったのですが、その芯にあるものは大好きです。
ある意味、こんな正直に正面突破な作品は珍しいですよね。

市井豊, 聴き屋の芸術学部祭
永らく待ってました。
というか、単行本出てたんですね、知らなかった…
ゆっくりでもいいので、また本出して欲しいです。

堀内公太郎, 「ご一緒にポテトはいかがですか」殺人事件
いつか読むだろうと思ってて、読んでなかった著者です。
森のクマさんも読んでみようと思います。
一年後かもしれないですが。

島田雅彦, 暗黒寓話集
こういうお話が普通に読めるといいですね。
昨今の「あやかし」ブームの影?でこういう空気が醸されると、
次の世代が豊かになると思うのですよ。







