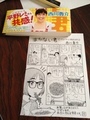最近では、西尾維新さんの「物語シリーズ」を筆頭に怪奇譚が流行っていますね。
今風に言えば「都市伝説」、少し前なら「お伽話」や「迷信」かな?
ひっくるめてフォークロアっていうのがいいかも。
これらの流行は定期的にやってくるらしく、金沢でも「随筆譚」や「三州奇談」など江戸時代にもブームがあったようす。
何となく、昔の日本人の感覚に近いと感じたのが、次のモノでした。
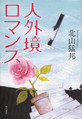 |
北山猛邦 人外境ロマンス ISBN 978-4-04-110472-9 [ honto / amazon / 国会図書館サーチ ] |
何というか、神話や昔話(というかその原型)って往々にしてお話が論理的でない。
意表をつく展開なものも多く、私が編集者だったらこんな創作は絶対ボツにするだろう、的なものが多々あります。
それでも数百年、時として数千年も残るのだから、不思議なものです。
まぁ、形を変えつつ生き長らえるものも多いのでしょうけれど。
そんな感覚を感じる作品というのは意外と少なくて、北山さんのコレもそのひとつ。
あくまで私の感じ方ですし、北山さんの文章が壊れているとかそういうお話ではないので悪しからず。