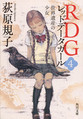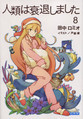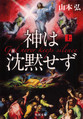最近ちょっと感じていたのが、「同世代の友人が愚痴っぽくなってきたなぁ」。
言っても、40代前半だから自然な流れかもしれないのですが、
高校時代から、大学時代からの、就職以降の友人総じてな感じがあります。
私は自他共に認めるように「変な人」に分類される方です。
ほとんど愚痴を言わない両親の下で育ち、
基本的に楽天的な性格なので、あまり愚痴は言わないと思います。
(自分ではそう思っていても、実際は言ってるのかもしれませんが)
相談だと思って話を聞いてると、相手は私の意見を求めていない。
そうか愚痴か、と思ってとりあえず話を聴く方に徹する。
友達なら別に普通のことだし、それだから嫌だというわけではありません。
さすがに、愚痴しか言わない人(それは友達ではないので)は勘弁願いたいですが。
年齢的に頭が硬くなっているのかなぁ、とかちょっと考えました。
私はどちらかといえば体は柔らかい方です。
頭も柔軟な方だと思っていましたが、次の本を読んでまだまだ硬いなと実感しました。
野尻抱介「南極点のピアピア動画」の参考文献から
「昆虫にとって〇〇とは何か?」という28の項目からなるエッセイ集のような本です。
〇〇には表題のコンビニの他に、車、人家、スーパー、自然保護、昆虫研究者、戦争などが入ります。
総じて言えば、昆虫にとって人とは何か?ということなのですが、
面白いのは、人にとって昆虫とは何か?とは対称ではないというところ。
日本には既知の昆虫が約3万種いて、未知のものを含むと10万種くらいだろうとのこと。
そういう事情に詳しい筆者が昆虫の立場から考察した「人」というものは、
一般人である私達が感じる「昆虫」とは見ている方向も大きさも違って当然です。
人が生きていくことは某かの命を奪っていることですは、誰しもが頭では分かっているつもりです。
例えば、私が昨年自転車で走ったことにより少なくとも18万匹の昆虫を殺しているようです。
私一人はもちろん、世界中の車などの走行により死んでいる昆虫の数は、しかしながら昆虫の全体からすればほんの些細な割合に過ぎすほとんど影響を与えないとか。
違う立場から考える。
これは簡単なようでいて難しい、ある程度その立場を理解していないと何の意味もないことですね。
むしろ、分ったような気になった分だけ始末に負えないのかも。
と反省を込めて、考えさせられました。
蛇足ですが、「昆虫にとって自然保護とは何か?」の項目は、私の中でこれまでモヤモヤしていた感じをクリヤーにしてくれました。